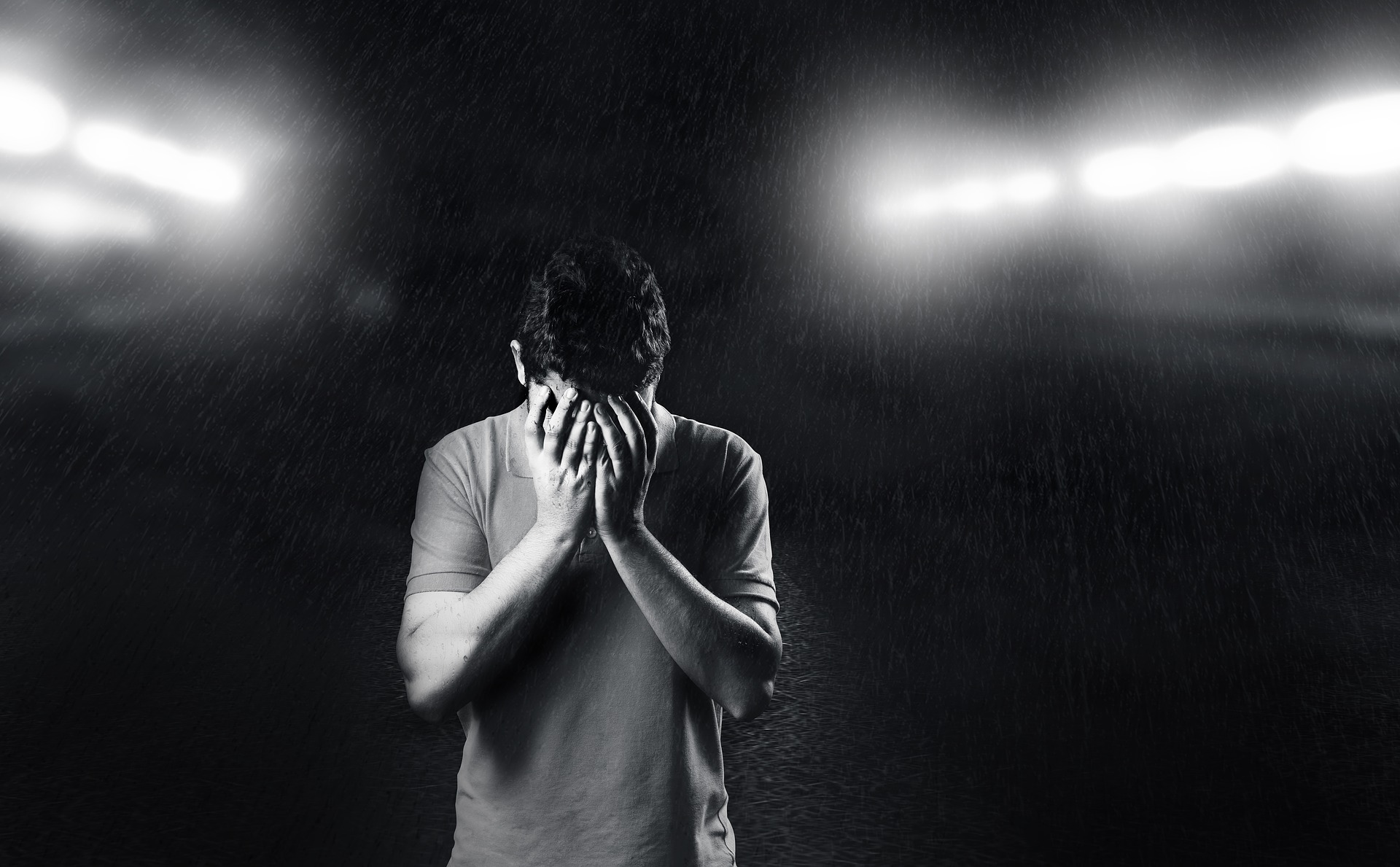今回の記事では、前回の「平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書」と併せて年末調整で勤め先に提出する
・配偶者の所得等の状況を確認する「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」
・生命保険料・地震保険料などを記載する「平成30年分給与所得者の保険料控除申告書」
昨年(2017年)までは、「保険料控除申告書 兼 配偶者控除控除申告書」という1枚の書類であったものが改正により様式が変更となり、こちらの2枚となりました。
この記事では、新しく追加された「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方を説明していきます。
勤め先によっては、提出のお願いをされる場合もありますが、以下に該当する方は配偶者控除・配偶者特別控除が受けられないため「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」については提出不要になると思われます。
・独身の方で配偶者が居ない場合
・提出する本人の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える方(給与のみの場合は、年収1,220万円超)
・配偶者の合計所得の見積額が123万円を超える方(給与のみの場合は、201万6,000円以上)
平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
 こちらが「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式になります。
こちらが「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式になります。
書類を紛失してしまった、あるいは書き間違えてしまった場合には「国税庁HP」からダウンロードして印刷し記入しましょう。
「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の仕方を説明していきます。
「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載手順
 「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順番です。(個人的には、この流れでの記入がスムーズに行くと思って紹介しています。)
「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順番です。(個人的には、この流れでの記入がスムーズに行くと思って紹介しています。)
順番に沿って説明していきます。
①本人の情報を記載する

(1)あなたの氏名(フリガナ)
記入されるご本人の名前とフリガナを記載します。
(2)あなたの住所又は居所
郵便番号と住所又は居所の住所を記載します。(原則は住民票があるところ)
②あなたの合計所得金額(見積額)を算出する

(1)~(7)の該当する所得がある場合に、「収入金額等a」ー「必要経費等b」=「所得金額」で金額を算出します。
これは人によってパターンがいくつも存在してしまうので、全部は説明出来ません。
いくつか国税庁HPに記載されているパターンを紹介します。
給与所得は、年末調整を受ける方は共通している事項なので「給与所得」の算出方法を説明します。
「収入金額等a」には、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった平成30年中の収入金額金額を記載します。
「必要経費等b」は、斜線が引かれているので省略です。
「所得金額」については、下記の画像の計算式に基づいて計算します。

※こちらの「3 所得の区分」は、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に記載されています。
【例:給与所得の金額の求め方】
給与等の収入金額が5,000,000円の場合には、「3,600,000円以上 6,599,999円以下」の部分を見ます。
計算式に当てはめていきます。
①5,000,000円÷4=1,250,000円(千円未満がある場合には切捨て)
②1,250,000円×3.2ー540,000=3,460,000円
となります。

【記載例】

先ほどの計算例で記載した場合には、上記のように記載します。
③あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記載する

②で計算した合計所得金額を記載します。
該当する(A)~(C)に当てはまる区分に☑を入れて、区分Ⅰに該当するA~Cを記載します。
【記載例】
今回計算した結果ですと、②で計算した3,460,000円を記載し900万円以下(A)に☑を入れて「A」を記載します。
④配偶者の合計所得金額(見積額)を記載する
 こちらは、配偶者の方の所得・合計所得額を記載する箇所になります。
こちらは、配偶者の方の所得・合計所得額を記載する箇所になります。
(1)~(7)の該当する所得がある場合に、「収入金額等a」ー「必要経費等b」=「所得金額」で金額を算出します。
配偶者の方が収入が無い場合は、「(1)~(7)の合計額」の部分に0と記載します。
【記載例】

⑤配偶者の情報を記載する

(1)配偶者の氏名(フリガナ)
(2)配偶者の個人番号
(3)配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所
(4)配偶者の生年月日
(5)老人控除対象配偶者(昭和24.1.1以前生)に該当する場合には○
(6)非居住者である配偶者(配偶者が非居住者である場合には〇)※該当する場合には、親族関係書類の添付が必要となります。扶養控除申告書を提出の際に添付している場合には重複となるため不要となります。
(7)生計を一にする事実(配偶者が非居住者である場合に送金金額等を記載します。)※送金関係書類の添付が必要となります。
※親族関係書類など提出義務がある方は、こちらの国税庁HPを参考に
どのような書類が必要かが記載されています。
【記載例】
 ④で計算した配偶者の方の合計所得額を記載します。
④で計算した配偶者の方の合計所得額を記載します。
該当する箇所①~④に☑を入れます。
今回、配偶者の本年中の合計所得金額は0で、年齢は70歳未満と仮定して記載例を作っています。
そのため「38万円以下かつ年齢70歳未満」に☑を入れます。
区分Ⅱに該当する①~④を記載します。
⑥控除額を計算する

区分Ⅰ、区分Ⅱに記載した区分を基に上記の表に当てはめて控除額を求めます。
【記載例】

【記載例】

区分Ⅰでは「A」
区分Ⅱでは「②」を記載しているため、配偶者控除の額のところに「380,000円」と記載します。
以上が「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方になります。
記載例で説明したパターンとしては、所得者本人の合計所得金額が900万以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合です。
この条件に該当される場合は、このパターンでの記載となります。
何パターンか記載例を紹介していきます。
記載例をパターン別に紹介
給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例2
所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合
・所得者本人は給与所得のみ(4,000,000円)
・配偶者も給与所得のみ(980,000円)

給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例3
所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合
・所得者本人は給与所得のみ(5,500,000円)
・配偶者も給与所得のみ(1,200,000円)

給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例4
所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
・所得者本人は給与所得のみ(3,200,000円)
・配偶者も給与所得のみ(1,700,000円)

給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例5
所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
・所得者本人は給与所得のみ(11,450,000円)
・配偶者も給与所得のみ(1,600,000円)

給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例6
所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合
・所得者本人は給与所得のみ(11,450,000円)
・配偶者も給与所得のみ(1,600,000円)

給与所得者の配偶者控除等申告書 記載例7
「年金所得の場合どのように記載するのか?」というコメントを頂いたので追記します。
配偶者が70歳以上で年金収入のみの場合
・所得者本人は給与所得のみ(4,000,000円)
・配偶者は年金のみ(2,000,000円)
 年金の場合は、雑所得の欄に記載します。
年金の場合は、雑所得の欄に記載します。
今回の場合は、収入金額等の部分に「2,000,000円」必要経費等の部分に「1,200,000円」と記載されます。
この「1,200,000円」については以下の表に当てはめて算出します。
 今回は70歳以上の人なので、受給者の区分が年齢65歳以上の人の部分を見ていきます。
今回は70歳以上の人なので、受給者の区分が年齢65歳以上の人の部分を見ていきます。
その年中の公的年金等の収入金額は、330万円以下なので控除額は120万円となります。
 より詳しく知りたい方は、こちらの国税庁HPを参考にして下さい。
より詳しく知りたい方は、こちらの国税庁HPを参考にして下さい。
配偶者の方が年金収入のみの場合でも、控除額の計算が出来れば後の流れは同じです。
記入する際の注意点
・あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合又は配偶者の合計所得の見積額が123万円を超える場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができません。
・夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
まとめ
 以上が「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載・記載例になります。
以上が「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載・記載例になります。
新しく追加された書類のため、困惑される方もいらっしゃると思います。
少しでも記載する際の手助けになれば幸いです。
個別の質問はパターンが多すぎて対応出来ないので、ご了承下さい。